گEˆُ‚ج‹خ–±ژٹشپC‹x“ْ‹y‚ر‹x‰ة‚ةٹض‚·‚é‹K‘¥‘و‚P‚Pڈً‚ة’è‚ك‚ç‚ê‚ؤ‚¢‚ـ‚·
‚±‚±‚ةژو‚èڈم‚°‚ؤ‚¢‚é‚à‚ج‚حپuٹT—vپv‚إ‚·‚ج‚إ
ڈع‚µ‚‚حژ––±گEˆُ‚ة‚¨گq‚ث‚‚¾‚³‚¢پB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚¢‚ë‚¢‚ë‚بڈêچ‡‚ة“ء•ت‹x‰ة‚ً‚ئ‚邱‚ئ‚ھ‚إ‚«‚ـ‚·
پ@پ@پ@پ@
پ@
پ@
پ@
‚»‚ꂼ‚ê‚جڈêچ‡‚ة‰‚¶‚ؤپCژو‚ê‚é“ْگ”‚ھˆل‚¢‚ـ‚·
پ@“ء•ت‹x‰ةگ\گ؟ڈ‘‚ة‹L“ü‚µ‚ؤڈٹ‘®’·‚جڈ³”F‚ًژَ‚¯‚ب‚¯‚ê‚خ‚¢‚¯‚ـ‚¹‚ٌپB
پiڈêچ‡‚ة‚و‚ء‚ؤ‚حپCڈط–¾ڈ‘“™‚ھ•K—v‚بڈêچ‡‚ھ‚ ‚è‚ـ‚·پBڈoژY‚جڈêچ‡پCڈoژY—\’è“ْڈط–¾ڈ‘‚ب‚اپjپ@
![]()
پ@‘و‚P‚Pڈً‚ج‚Pچ†پ@
‘I‹“Œ ‚â‚»‚ج‘¼Œِ–¯‚ئ‚µ‚ؤ‚جŒ —ک‚ًچsژg‚·‚éڈêچ‡
پ@پ@پ@‚»‚ج“s“x•K—v‚ئ”F‚ك‚é“ْ–”‚حژٹش‚ئ‚ê‚ـ‚·

![]()
پ@پ@‘و‚P‚Pڈً‚ج‚Qچ†پ@
چظ”»ˆُپCڈطگlپCٹس’èگlپCژQچlگl“™‚ئ‚µ‚ؤچ‘‰ïپCچظ”»ڈٹپC’n•ûŒِ‹¤’c‘ج‚ج‹c‰ï–”‚ح پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@
‚»‚ج‘¼‚جٹ¯Œِڈگ‚ضڈo“ھ‚·‚éڈêچ‡
پ@پ@پ@‚»‚ج“s“x•K—v‚ئ”F‚ك‚é“ْ–”‚حژٹش ‚ئ‚ê‚ـ‚·
پ–Œؤڈoڈَ‚ھ•K—v‚إ‚·
![]() ‘و‚P‚Pڈً‚ج‚Rچ†
‘و‚P‚Pڈً‚ج‚Rچ†
چœگ‘ˆعگA‚ج‚½‚ك‚جچœگ‘ژل‚µ‚‚ح––ڈ½ŒŒٹ²چ×–EˆعگA‚ج‚½‚ك‚ج––ڈ½ŒŒٹ²چ×–E‚ج’ٌ‹ںٹَ–]ژز‚ئ‚µ‚ؤ‚»‚ج“oک^‚ًژہژ{‚·‚éژز‚ة‘خ‚µ‚ؤ“oک^‚جگ\ڈo‚ًچs‚¢پC–”‚ح”z‹ôژزپC•ƒ•êپCژq‹y‚رŒZ’يژo–…ˆبٹO‚جژز‚ةچœگ‘ˆعگA‚ج‚½‚ك‚جچœگ‘ژل‚µ‚‚ح––ڈ½ŒŒٹ²چ×–EˆعگA‚ج‚½‚ك‚ج––ڈ½ŒŒٹ²چ×–E‚ً’ٌ‹ں‚·‚éڈêچ‡
![]() ‰ئ‘°ˆبٹO‚ةچœگ‘ˆعگA‚ً’ٌ‹ں‚·‚éڈêچ‡‚ةژو‚ê‚ـ‚·
‰ئ‘°ˆبٹO‚ةچœگ‘ˆعگA‚ً’ٌ‹ں‚·‚éڈêچ‡‚ةژو‚ê‚ـ‚·
![]() ƒhƒiپ[“oک^‚ً‚·‚éژ‚ة‚àژو‚ê‚ـ‚·
ƒhƒiپ[“oک^‚ً‚·‚éژ‚ة‚àژو‚ê‚ـ‚·
پ@پ@پ@‚»‚ج“s“x•K—v‚ئ”F‚ك‚é“ْ–”‚حژٹش‚ئ‚ê‚ـ‚·

![]()
پ@‘و‚P‚Pڈً‚ج‚Sچ†
گEˆُ‚ھژ©”“I‚ةپC‚©‚آپC•ٌڈV‚ً“¾‚ب‚¢‚إژں‚ةŒf‚°‚éژذ‰ï‚ةچvŒ£‚·‚éٹˆ“®پiچ‘پC’n•ûŒِ‹¤’c‘ج–”‚حŒِ‹¤“I’c‘ج‚ھژهچأ‚µپC–”‚حŒم‰‡‚·‚éٹˆ“®‚ةŒہ‚éپBپj‚ًچs‚¤ڈêچ‡پ@
پ@
پ¦Œ´‘¥‚ئ‚µ‚ؤ‰ھژRŒ§“à‚إ‚جٹˆ“®‚ةŒہ‚éپB‚½‚¾‚µ‰ھژRŒ§–¯‚ھژQ‰ء‚·‚éٹˆ“®‚ة‚آ‚¢‚ؤ‚حپAŒ§ٹO‚إ‚à‘خڈغ‚ئ‚ب‚éپB‚ـ‚½پAگEˆُ‚ھڈٹ‘®‚·‚é’¬“à‰ï‚ب‚ا’n‰ڈپAŒŒ‰ڈ‚ةŒW‚é’c‘ج‚ھگê‚ç“–ٹY’c‘ج‚ج‚½‚ك‚ةچs‚¤ٹˆ“®‚ح‘خڈغ‚ئ‚µ‚ب‚¢
پ@—ï”N‚ة‚¨‚¢‚ؤپC‚T“ْ‚ً‰z‚¦‚ب‚¢”حˆح“à‚إ•K—v‚ئ”F‚ك‚é“ْ–”‚حژٹش‚ئ‚ê‚ـ‚·پ@پ@پ@
پ@پ@پ@ژٹش‚إژو“¾‚µ‚½ڈêچ‡‚Vژٹش‚S‚T•ھ‚ً‚à‚ء‚ؤ‚P“ْ‚ئٹ·ژZ‚µ‚ـ‚·
پ–ٹˆ“®Œv‰وڈ‘‚ھ•K—v‚إ‚·

ƒCپ@•غŒ’پCˆم—أ–”‚ح•ںژƒ‚ج‘گi‚ًگ}‚éٹˆ“®پ@
پ–گg‘جڈلٹQژز—أŒىژ{گفپC“ء•ت—{ŒىکVگlƒzپ[ƒ€‚»‚ج‘¼‚جژه‚ئ‚µ‚ؤگg‘جڈمژل‚µ‚‚حگ¸گ_ڈم‚جڈلٹQ‚ھ‚ ‚é‚à‚ج–”‚ح•‰ڈ‚µپCژل‚µ‚‚حژ¾•a‚ة‚©‚©‚ء‚½‚à‚ج‚ة‘خ‚µ‚ؤ•K—v‚ب‘[’u‚ًچu‚¸‚邱‚ئ‚ً–ع“I‚ئ‚·‚é•ت•\‚ةŒf‚°‚éژ{گف‹y‚ر‚±‚ê‚ç‚ةڈ€‚¸‚éژ{گف‚إ‚ ‚ء‚ؤگlژ–ˆدˆُ‰ï‚ھ”F‚ك‚éژ{گف‚ة‚¨‚¯‚éٹˆ“®•ہ‚ر‚ةگg‘جڈمژل‚µ‚‚حگ¸گ_ڈم‚جڈلٹQپC•‰ڈ–”‚حژ¾•a‚ة‚و‚èڈي‘ش‚ئ‚µ‚ؤ“ْڈيگ¶ٹˆ‚ً‰c‚ق‚ج‚ةژxڈل‚ھ‚ ‚éژز‚ج‰îŒى‚»‚ج‘¼‚ج“ْڈيگ¶ٹˆ‚ًژx‰‡‚·‚éٹˆ“®پ@پ@
| پyپ@•تپ@•\پ@پz |
| گg‘جڈلٹQژز•ںژƒ–@‘و‚Tڈً‘و‚Pچ€‚ة‹K’è‚·‚éگg‘جڈلٹQژزچXگ³ژ{گفپCگg‘جڈلٹQژز—أŒىژ{گفپCگg‘جڈلٹQژز•ںژƒƒzپ[ƒ€پCگg‘جڈلٹQژزژِژYژ{گفپCگg‘جڈلٹQژز•ںژƒƒZƒ“ƒ^پ[پC•â‘•‹ïگ»چىژ{گف,–س“±Œ¢ŒP—ûژ{گف‹y‚رژ‹’®ٹoڈلٹQژزڈî•ٌ’ٌ‹ںژ{گف |
| ’m“IڈلٹQژز•ںژƒ–@‘و‚Tڈً‘و‚Pچ€‚ة‹K’è‚·‚é’m“IڈلٹQژزƒfƒCƒTپ[ƒrƒXƒZƒ“ƒ^پ[پC’m“IڈلٹQژزچXگ³ژ{گفپC’m“IڈلٹQژزژِژYژ{گفپC’m“IڈلٹQژز’ت‹خ—¾‹y‚ر’m“IڈلٹQژز•ںژƒƒzپ[ƒ€ |
| گ¸گ_•غŒ’‹y‚رگ¸گ_ڈلٹQژز•ںژƒ‚ةٹض‚·‚é–@—¥‘و‚T‚Oڈً‚ج‚Q‘و‚Pچ€‚ة‹K’è‚·‚éگ¸گ_ڈلٹQژزگ¶ٹˆŒP—ûژ{گفپCگ¸گ_ڈلٹQژزژِژYژ{گفپCگ¸گ_ڈلٹQژز•ںژƒƒzپ[ƒ€پCگ¸گ_ڈلٹQژز•ںژƒچHڈê‹y‚رگ¸گ_ڈلٹQژز’nˆوگ¶ٹˆژx‰‡ƒZƒ“ƒ^پ[ |
| ژ™“¶•ںژƒ–@‘و‚Vڈً‚ة‹K’è‚·‚é’m“IڈلٹQژ™ژ{گفپC’m“IڈلٹQژ™’ت‰€ژ{گفپC–س‚낤‚ ژ™ژ{گفپCژˆ‘ج•sژ©—Rژ™ژ{گفپCڈdڈاگSگgڈلٹQژ™ژ{گف‹y‚رڈîڈڈڈلٹQژ™’Zٹْژ،—أژ{گف |
| کVگl•ںژƒ–@‘و‚Tڈً‚ج‚R‚ة‹K’è‚·‚éکVگlƒfƒCƒTپ[ƒrƒXƒZƒ“ƒ^پ[پCکVگl’Zٹْ“üڈٹژ{گفپCپ@—{ŒىکVگlƒzپ[ƒ€‹y‚ر“ء•ت—{ŒىکVگlƒzپ[ƒ€پ@ |
| گ¶ٹˆ•غŒى–@‘و‚R‚Wڈً‘و‚Pچ€‚ة‹K’è‚·‚é‹~Œىژ{گفپCچXگ³ژ{گف‹y‚رˆم—أ•غŒىژ{گف |
| ‰îŒى•غŒ¯–@‘و‚Wڈً‘و‚Q‚Wچ€‚ة‹K’è‚·‚é‰îŒىکVگl•غŒ’ژ{گف‚¨‚و‚ر‘و‚Q‚Xچ€‚ة‹K’è‚·‚é‰îŒىˆم—أ‰@ |
| ˆم—أ–@‘و‚Pڈً‚ج‚T‘و‚Pچ€‚ة‹K’è‚·‚é•a‰@ |
| ٹwچZ‹³ˆç–@‘و‚Pڈً‚ة‹K’è‚·‚é–سٹwچZپC‚낤ٹwچZ‹y‚ر—{ŒىٹwچZ |
ƒچپ@ژذ‰ï‹³ˆç‚جگ„گi‚ًگ}‚éٹˆ“®پ@
پ–ڈء”ïژز‹³ˆçٹˆ“®پCگ¶ٹUٹwڈK‚جگ„گiٹˆ“®“™
ƒnپ@‚ـ‚؟‚أ‚‚è‚جگ„گi‚ًگ}‚éٹˆ“®
پ–ٹدŒُƒ}ƒbƒv‚أ‚‚èپC—ًژjپE•¶‰»پEŒiٹد“™‚ج’nˆو‚ج“ءگ«‚ًٹˆ‚©‚µ‚½‚ـ‚؟‚أ‚‚èٹˆ“®“™
پ–چ‚—îژزپCڈلٹQژز“™‚ة”z—¶‚µ‚½‚ـ‚؟‚أ‚‚èٹˆ“®“™
ƒjپ@ٹwڈpپC•¶‰»پCŒ|ڈpپC–”‚حƒXƒ|پ[ƒc‚جگU‹»‚ًگ}‚éٹˆ“®
پ–“`“•¶‰»پEŒ|ڈp‚ج“`ڈ³پCگU‹»“™پCƒXƒ|پ[ƒc‚ج•پ‹yپCƒXƒ|پ[ƒc‘ه‰ï“™‚ج‰^‰c‹¦—ح‚ةٹض‚·‚éٹˆ“®“™
ƒzپ@ٹآ‹«‚ج•غ‘S‚ًگ}‚éٹˆ“®
پ–گX—ر•غ‘Sٹˆ“®پCگ´‘|”ü‰»ٹˆ“®“™
ƒwپ@چذٹQ‹~‰‡ٹˆ“®
پ–’nگkپC–\•—‰JپC•¬‰خ“™‚ة‚و‚èچذٹQ‹~ڈ•–@‚ة‚و‚é‹~ڈ•‚جچs‚ي‚ê‚é’ِ“x‚ج‹K–ح‚جچذٹQ‚ھ”گ¶‚µ‚½”يچذ’n–”‚ح‚»‚جژü•س‚ج’nˆو‚ة‚¨‚¯‚éگ¶ٹˆٹضکA•¨ژ‘‚ج”z•z‚»‚ج‘¼‚ج”يچذژز‚ًژx‰‡‚·‚éٹˆ“®
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@”يچذ’n–”‚ح‚»‚جژü•س‚ج’nˆو‚ئ‚حپHپ@پ@پ@
”يٹQ‚ھ”گ¶‚µ‚½ژs’¬‘؛پi“ء•ت‹و‚ًٹـ‚قپj–”‚ح‚»‚ج‘®‚·‚é“s“¹•{Œ§ژل‚µ‚‚ح‚±‚ê‚ة—×گع‚·‚é“s“¹•{Œ§پ@پ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚»‚ج‘¼‚ج”يچذژز‚ًژx‰‡‚·‚éٹˆ“®‚ئ‚حپH
‹ڈ‘î‚ج‘¹‰َپCگ…“¹پC“d‹CپCƒKƒX‚جژص’f“™‚ة‚و‚è“ْڈيگ¶ٹˆ‚ً‰c‚ق‚ج‚ةژxڈل‚ھگ¶‚¶‚ؤ‚¢‚éژز‚ة‘خ‚µ‚ؤچs‚¤گ†‚«ڈo‚µپC”ً“ïڈêڈٹ‚إ‚جگ¢کbپC‚ھ‚ê‚«‚ج“P‹ژ‚»‚ج‘¼•K—v‚ب‰‡ڈ•
ƒgپ@’nˆوˆہ‘Sٹˆ“®
پ–”ئچكپCŒً’تژ–Œج“™‚ة‚و‚é”يٹQ‚ج–¢‘R–hژ~پCٹg‘ه–hژ~‚ج‚½‚ك‚جٹˆ“®“™
ƒ`پ@چ‘چغ‹¦—ح‚جٹˆ“®
پ–ٹCٹO‚ض‚ج•¨ژ‘‰‡ڈ•ٹˆ“®پC—¯ٹwگ¶‚ض‚جژx‰‡ٹˆ“®“™
ƒٹپ@’jڈ—‹¤“¯ژQ‰وژذ‰ï‚جŒ`گ¬‚ج‘£گi‚ًگ}‚éٹˆ“®
پ–گ«چ·•ت‚ً‚ب‚‚·ٹˆ“®پCƒZƒNƒVƒƒƒ‹ƒnƒ‰ƒXƒپƒ“ƒg‚ً–hژ~‚·‚éٹˆ“®“™
ƒkپ@ژq‚ا‚à‚جŒ’‘Sˆçگ¬‚ًگ}‚éٹˆ“®
پ–‚¢‚¶‚ك‘ٹ’kپCٹw“¶•غˆç‚جڈ[ژہپCژq‚ا‚à‚ض‚ج–ىٹOٹwڈK‚ً’ٌ‹ں‚·‚éٹˆ“®پCگآڈ”N‚ج”ٌچs–hژ~‚ج‚½‚ك‚جٹˆ“®“™
ƒ‹پ@گlŒ ‚ج—iŒى–”‚ح•½کa‚جگ„گi‚ًگ}‚éٹˆ“®‚إ‚ ‚ء‚ؤپCگlژ–ˆدˆُ‰ï‚ھ’è‚ك‚é‚à‚ج
پ–گlژ–ˆدˆُ‰ï‚ھ’è‚ك‚é‚à‚ج‚ئ‚حپCگlŒ گNٹQپCچ·•ت‚ً‚ب‚‚·‚½‚ك‚جŒ[”ٹˆ“®پCگي‘ˆ‘جŒ±‚ج‹Lک^پE“`ڈ³ٹˆ“®“™پ@پ@پ@
![]()
‘و‚P‚Pڈً‚ج‚Tچ†
پ@ƒCپ@ٹ´گُڈا‚ج—\–h‹y‚رٹ´گُڈا‚جٹ³ژز‚ة‘خ‚·‚éˆم—أ‚ةٹض‚·‚é–@—¥پi•½گ¬‚P‚O”N–@—¥‘و‚P‚P‚Sچ†پj‚ج‹K’è‚ة‚و‚éŒً’ت‚جگ§Œہ–”‚حژص’f‚جڈêچ‡
پ@ƒچپ@•—گ…گk‰خچذ‚»‚ج‘¼”ٌڈيچذٹQ‚ة‚و‚éŒً’تژص’f‚جڈêچ‡
پ@ƒnپ@ƒC–”‚حƒچ‚ج‚ظ‚©پCŒً’ت‹@ٹض‚جژ–Œج“™•s‰آچR—ح‚ة‚و‚éڈêچ‡
پ@
پ@پ@پ@پ@‚»‚ج“s“x•K—v‚ئ”F‚ك‚é“ْ–”‚حژٹشپ@‚ئ‚ê‚ـ‚·
پ–ڈط–¾ڈ‘‚ھ•K—v‚إ‚·
![]() ‘و‚P‚Pڈً‚ج‚Uچ†پE‚Vچ†
‘و‚P‚Pڈً‚ج‚Uچ†پE‚Vچ†
| پ@ پ@•—گ…گk‰خچذ‚»‚ج‘¼‚ج“Vچذ’n•د‚ة‚و‚èپCژں‚ج‚¢‚¸‚ê‚©‚ةٹY“–‚·‚éڈêچ‡پC‚PڈTٹش‚ً’´‚¦‚ب‚¢”حˆح“à‚إ‚»‚ج“s“x•K—v‚ئ”F‚ك‚é“ْ–”‚حژٹش پ@ƒCپ@گEˆُ‚جŒ»ڈZڈٹ‚ھ–إژ¸‚µپC–”‚ح‘¹‰َ‚µ‚½‚½‚كپC“–ٹYگEˆُ‚ھ‚»‚ج•œ‹Œچى‹ئ“™‚ًچs‚¢پC–”‚حˆêژ“I‚ة”ً“‚ؤ‚¢‚éڈêچ‡ پ@ƒچپ@گEˆُ‹y‚ر“–ٹYگEˆُ‚ئ“¯ˆê‚جگ¢‘ر‚ة‘®‚·‚éژز‚جگ¶ٹˆ‚ة•K—v‚بگ…پCگH—ئ“™‚ھ’ک‚µ‚•s‘«‚µ‚ؤ‚¨‚èپC“–ٹYگEˆُˆبٹO‚ة‚ح‚»‚ê‚ç‚جٹm•غ‚ًچs‚¤‚±‚ئ‚ھڈo—ˆ‚ب‚¢ڈêچ‡ پ@ƒnپ@ƒC–”‚حƒچ‚ج‚ظ‚©پC‚±‚ê‚ç‚ةڈ€‚¸‚éڈêچ‡ پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ–ڈط–¾ڈ‘‚ھ•K—v‚إ‚·پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ |
|
| پ@ پ@•—گ…گk‰خچذ‚»‚ج‘¼‚ج”ٌڈيچذٹQ‚ة‚و‚èگEˆُ‚جŒ»ڈZ‹ڈ‚ج–إژ¸پC”j‰َپCŒً’تژص’f‹y‚رگg‘ج‚ةٹëٹQ‚ً‹y‚ع‚·‚±‚ئ‚ھ—\‘ھ‚³‚ê‚é‚ئ”C–½Œ ژز‚ھ”F‚ك‚éڈêچ‡پC‚»‚ج“s“x•K—v‚ئ”F‚ك‚é“ْ–”‚حژٹش |
![]() ‘و‚P‚Pڈً‚ج‚Wچ†
‘و‚P‚Pڈً‚ج‚Wچ†
‚آ‚ي‚èپEŒںگfپE’ت‹خٹةکaپE•ھ•ط‚ب‚ا‚ة‚آ‚¢‚ؤ‚»‚ꂼ‚êˆب‰؛‚ج‚ئ‚¨‚è‚ئ‚ê‚ـ‚·
پ@پ@گEˆُ‚ج•ھ•ط
گEˆُ‚ج•ھ‚ׂٌ‚جڈêچ‡پC‚»‚ج•ھ‚ׂٌ‚ج—\’è“ْ‘O‚WڈTٹش–عپi‘½‘ظ”DگP‚جڈêچ‡‚ح‚P‚SڈTٹش–عپj‚ة“–‚½‚é“ْ‚©‚çپC•ھ‚ׂٌ‚ج“ْŒم‚WڈTٹش–ع‚ة“–‚½‚é“ْ‚ـ‚إ‚جٹْٹش“à‚ة‚¨‚¢‚ؤ•K—v‚ئ”F‚ك‚éٹْٹش
—\’è“ْ‚ج‘O“ْ‚©‚ç‚WڈTٹشژY‘O“ء•ت‹x‰ة‚ھ‚ئ‚ê‚ـ‚·پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@
•ھ‚ׂٌ‚ج“ْ‚ھ—\’è“ْ‚و‚艄‚ر‚½ڈêچ‡پC‰„‚ر‚½•ھ‚¾‚¯’·‚”F‚ك‚ç‚ê‚ـ‚·
‚ـ‚½پC—\’è“ْ‚و‚è‘پ‚‚ب‚ء‚½ڈêچ‡پC‘پ‚‚ب‚ء‚½•ھ‚¾‚¯’Z‚‚ب‚è‚ـ‚·پ@پ@پ@پ@پ@
پ–پ@ڈoژY“ْ—\’è“ْڈط–¾ڈ‘‚ھ•K—v‚إ‚·پ@پ@پ@
![]() ‘و‚P‚Pڈً‚ج‚Xچ†
‘و‚P‚Pڈً‚ج‚Xچ†
پ@پ@ƒCپ@پ@•غŒ’ژw“±پEŒ’چNگfچ¸پi”D•wŒںگfپj
”DگP’†–”‚ح•ھ‚ׂٌ‚ج“ْŒم‚P”Nˆب“à‚جڈ—گ«گEˆُ‚ھپC•êژq•غŒ’–@‘و‚P‚Oڈً‚ة‹K’è‚·‚é•غŒ’ژw“±–”‚ح“¯–@‘و‚P‚Rڈً‚ة‹K’è‚·‚錒چNگfچ¸‚ًژَ‚¯‚éڈêچ‡
پ@پ@پ@پ@پ@”DگP–‚Q‚RڈT‚ـ‚إ‚حپ@ ‚SڈTٹش‚ة‚P‰ٌپC
پ@پ@پ@پ@پ@”DگP–‚Q‚SڈT‚©‚ç–‚R‚TڈT‚ـ‚إ‚ح پ@‚QڈTٹش‚ة‚P‰ٌپC
پ@پ@پ@پ@پ@”DگP–‚R‚UڈT‚©‚ç•ھ‚ׂٌ‚ـ‚إ‚ح پ@‚PڈTٹش‚ة‚P‰ٌپCپ@
پ@پ@پ@پ@پ@•ھ‚ׂٌŒم‚P”N‚ـ‚إ‚حپ@ ‚»‚جٹش‚ة‚P‰ٌپ@
پ@پiˆمژt“™‚ج“ء•ت‚جژwژ¦‚ھ‚ ‚ء‚½ڈêچ‡‚ة‚ح‚¢‚¸‚ê‚جٹْٹش‚ة‚آ‚¢‚ؤ‚à‚»‚جژwژ¦‚³‚ꂽ‰ٌگ”پj
ˆب“à‚»‚ꂼ‚ê‚P‰ٌ‚P“ْ‚جگ³‹K‚ج‹خ–±ژٹش‚ج”حˆح“à‚إ‚»‚ج“s“x•K—v‚ئ”F‚ك‚éژٹش
پ@پ@ƒچپ@پ@’ت‹خٹةکa
”DگP’†‚جڈ—گ«گEˆُ‚ھ’ت‹خ‚ة—ک—p‚·‚éŒً’ت‹@ٹض‚جچ¬ژG‚ج’ِ“x‚»‚ج‘¼‚ج’ت‹خژ–ڈî‚ھپC•ê‘ج–”‚ح‘ظژ™‚جŒ’چN•غژ‚ة“ء‚ة‰e‹؟‚ھ‚ ‚é‚ئ”F‚ك‚ç‚ê‚éڈêچ‡گ³‹K‚ج‹خ–±ژٹش‚جژn‚ك–”‚حڈI‚ي‚è‚ة‚¨‚¢‚ؤپC‚P“ْ‚ً’ت‚¶‚ؤ‚Pژٹش‚ً’´‚¦‚ب‚¢”حˆح“à‚إ•K—v‚ئ”F‚ك‚éژٹش
Œً’ت‹@ٹض‚جچ¬ژG‚ج’ِ“xپ@‚ئ‚ح
پ@گEˆُ‚ھ’تڈي‚ج‹خ–±‚ً‚·‚éڈêچ‡‚ج“o’،–”‚ح‘ق’،‚جژٹش‘ر‚ة‚¨‚¯‚éڈي—ل‚ئ‚µ‚ؤ—ک—p‚·‚éŒً’ت‹@ٹض‚جچ¬ژG‚ج’ِ“x‚ً‚¢‚¤
![]() پ@•ê‘ج–”‚ح‘ظژ™‚جŒ’چN•غژ‚ة‰e‹؟‚ھ‚ ‚éپ@‚ئ‚ح
پ@•ê‘ج–”‚ح‘ظژ™‚جŒ’چN•غژ‚ة‰e‹؟‚ھ‚ ‚éپ@‚ئ‚ح
•êژq•غŒ’–@‘و‚P‚Oڈً‚ة‹K’è‚·‚é•غŒ’ژw“±–”‚ح“¯–@‘و‚P‚Rڈً‚ة‹K’è‚·‚錒چNگRچ¸‚ةٹî‚أ‚ژw“±ژ–چ€‚ة‚و‚è”»’f‚·‚é‚à‚ج‚ئ‚·‚é
پ@پ@ƒnپ@پ@”DگPڈلٹQپi‚آ‚ي‚èپjپ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@
”DگP’†‚جڈ—گ«گEˆُ‚ھ”DگP‚ة‹Nˆِ‚·‚éڈلٹQپi‚آ‚ي‚èپj‚ج‚½‚ك‹خ–±‚·‚邱‚ئ‚ھچ¢“ï‚إ‚ ‚é‚ئ”F‚ك‚ç‚ê‚éڈêچ‡پC‚»‚جٹْٹش‚ة‚¨‚¢‚ؤ‚P‚S“ْˆب“à‚ج“ْ–”‚حژٹش
پ@پ@پ@پ@ƒjپ@پ@گ¶—
پ@پ@پ@پ@گ¶—“ْ‚ج‹خ–±‚ھ’ک‚µ‚چ¢“ï‚بڈ—گ«گEˆُ‚جگ¶—“ْ‚جڈêچ‡‚Q“ْ‚ً’´‚¦‚ب‚¢”حˆح“à‚إ‚»‚ج“s“x•K—v‚ئ”F‚ك‚é“ْ–”‚حژٹش
پ@پ@پ@پ@پ@ƒzپ@پ@•s”Dڈا–”‚ح•sˆçڈا‚ج‚½‚ك‚جژ،—أ
پ@پ@پ@پ@ˆم—أ‹@ٹض‚ة‚¨‚¢‚ؤˆمژt“™‚ھچs‚¤•s”Dڈا–”‚ح•sˆçڈا‚ج‚½‚ك‚جژ،—أچsˆ×پi“–ٹYژ،—أ‚ةŒW‚éŒںچ¸“™‚ًٹـ‚قپj‚ًژَ‚¯‚éڈêچ‡
پ@پ@پ@پ@—ï”N‚إ‚P‚O“ْ‚ً’´‚¦‚ب‚¢”حˆح“à‚إ•K—v‚ئ”F‚ك‚é“ْ–”‚حژٹش

پ@پ@
![]() ‘و‚P‚Pڈً‚ج‚P‚Oچ†
‘و‚P‚Pڈً‚ج‚P‚Oچ†
پ@پ@گEˆُ‚ھگ¶Œم–‚R”N‚ة’B‚µ‚ب‚¢گ¶ژ™‚ًˆç‚ؤ‚éڈêچ‡پCژں‚ةŒf‚°‚éژٹش‚ج‹و•ھ‚ة‰‚¶پC‚»‚ꂼ‚êژں‚ةŒf‚°‚éژٹش‚ً’´‚¦‚ب‚¢”حˆح“à‚إ‚»‚ج“s“x•K—v‚ئ”F‚ك‚éژٹشپ@پ@
پ@پ@پ@پ@ڈ—ژqگEˆُ‚جگ\گ؟‚حپC•K‚¸”F‚ك‚ç‚ê‚é
پ@پ@پ@پ@’jگ«گEˆُ‚ة‚ ‚ء‚ؤ‚حˆçژ™ژٹش‚جڈ³”F‚ًژَ‚¯‚و‚¤‚ئ‚·‚éژٹش‚ةپC”z‹ôژز‚ھ—{ˆç‚إ‚«‚éژز‚حڈœ‚©‚ê‚é‚ھپA
پ@پ@پ@پ@چب‚ھگê‹ئژه•w‚إ‚ ‚ء‚ؤ‚àپCژذ‰ï’ت”Oڈم‘أ“–‚ئ”F‚ك‚ç‚ê‚éژ–ڈîپiچب–{گl‚ج•a‹CپCگe‚جٹإŒى“™پj‚ة‚و‚è•غˆç‚ھچ¢“ï‚إ‚ ‚éڈêچ‡‚ة‚ح”F‚ك‚ç‚ê‚é
ƒCپ@پ@گ¶Œم–‚P”N‚ة’B‚µ‚ب‚¢گ¶ژ™‚ًˆç‚ؤ‚éٹْٹش
‚P“ْ‚Q‰ٌˆب“à‚P‰ٌ‚U‚O•ھ
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@
پ@پi’jگ«گEˆُ‚ة‚ ‚ء‚ؤ‚حپC”z‹ôژز‚ھ—ک—p‚µ‚ؤ‚¢‚éˆçژ™ژٹش‚ً‚Qژٹش‚©‚猸‚¶‚½ژٹش‚ًŒہ“x‚ئ‚·‚éپj
![]()
![]()
پ@پ@پ@
ƒچپ@پ@گ¶Œم–‚P”Nپ`–‚R”N‚ة’B‚µ‚ب‚¢گ¶ژ™‚ًˆç‚ؤ‚éٹْٹش
‚P“ْ‚Q‰ٌˆب“à‚P‰ٌ‚R‚O•ھ
پi’jگ«گEˆُ‚ة‚ ‚ء‚ؤ‚حپC”z‹ôژز‚ھ—ک—p‚µ‚ؤ‚¢‚éˆçژ™ژٹش‚ً‚Pژٹش‚©‚猸‚¶‚½ژٹش‚ًŒہ“x‚ئ‚·‚éپj
![]() ‘و‚P‚Pڈً‚ج‚P‚Pچ†‚ج‚Q
‘و‚P‚Pڈً‚ج‚P‚Pچ†‚ج‚Q
ƒCپ@ژں‚ج‡@پ`‡F‚جژ–—R‚ةٹY“–‚·‚éڈêچ‡پA—ï”N‚إ‚T“ْˆب“àپi’†ٹwچZ‘²‹ئ‚ـ‚إ‚جژq‚ھ“ٌگlˆبڈم‚¢‚éگEˆُ‚ح‚U“ْˆب“à‹y‚ر–‚P‚Qچخ‚ة’B‚·‚é“ْˆبŒم‚جچإڈ‰‚ج‚RŒژ‚R‚P“ْ‚ـ‚إ‚جژq‚ھ‚Qگlˆبڈم‚ ‚é‚ئ‚«‚ح‚P‚O“ْˆب“àپj‚ج“ْ–”‚حژٹش
‡@ژq‚ھ•‰ڈپEژ¾•a‚ة‚و‚èگEˆُ‚جٹإŒى‚ً•K—v‚ئ‚·‚éڈêچ‡
‡Aژq‚ةŒ’چNگf’fپE—\–hگعژي‚ًژَ‚¯‚³‚¹‚éڈêچ‡
‡Bژq‚ھچفگذ‚·‚éٹwچZ“™‚ھژہژ{‚·‚éچsژ–پi“üٹwژ®پCژِ‹ئژQٹد“™پj‚ةڈoگب‚·‚éڈêچ‡
‡Cچ‘پE’n•ûŒِ‹¤’c‘ج“™‚ھژهچأ‚·‚镃گeپE•êگe‹³ژ؛‚ةژq“¯”؛‚إژQ‰ء‚·‚éڈêچ‡
‡Dڈ•a‚ج‚½‚ك“o‰؛چZ‚ةگe‚ج‰îڈ•‚ً•K—v‚ئ‚·‚éژq–”‚ح•s“oچZ‚جژq‚جٹwچZ“™‚ض‚ج‘—Œ}‚ًچs‚¤ڈêچ‡
‡Eژq‚ھچفگذ‚·‚éٹwچZ“™‚ج‚o‚s‚`ٹˆ“®‚ةژQ‰ء‚·‚éڈêچ‡
‡F•ْ‰غŒمژ™“¶ƒNƒ‰ƒu‚ج‰^‰cˆدˆُ‰ï“™‚ةژQ‰ء‚·‚éڈêچ‡
پ@پ@پ@پ@پ¦پuژqپv‚ئ‚حگEˆُ‚ھ—{ˆç‚·‚é’†ٹwچZ‘²‹ئ‚ـ‚إ‚جژq‚ً‚¢‚¤
‡G”’BڈلٹQ‚ج‚ ‚éژq‚ًژ‚آگEˆُ‚ھپAژq‚ج•ْ‰غŒمƒfƒCƒTپ[ƒrƒX‚جچsژ–‚ضژQ‰ء‚·‚éڈêچ‡
‡Hگf’f–¼‚ج‚آ‚¢‚ؤ‚¢‚é”’BڈلٹQ‚إگe‚ج‰îڈ•‚ً•K—v‚ئ‚·‚éژq‚ج•ْ‰غŒمƒfƒCƒTپ[ƒrƒX‚ض‚ج‘—Œ}‚ً‚·‚éڈêچ‡
‡I’ت‹‰ژw“±‹³ژ؛‚ةژq“¯”؛‚إژQ‰ء‚·‚éڈêچ‡
پ@پ@•êژq•غŒ’–@‘و‚P‚Qڈً‹y‚ر‘و‚P‚Rچ†‚ة‹K’è‚·‚錒چNگfچ¸•ہ‚ر‚ةٹwچZ•غŒ’–@‘و‚Sڈً‚ة‹K’è‚·‚éڈAٹwژŒ’چNگf’f‚ً‚¢‚¢‚ـ‚·پB |
پ@پ@—\–hگعژي–@‘و‚Rڈً–”‚حŒ‹ٹj—\–h–@‘و‚P‚Rڈً‹y‚ر‘و‚P‚Sڈً‚ةٹî‚أ‚—\–hگعژيپiƒcƒxƒ‹ƒNƒٹƒ“”½‰Œںچ¸‚ًٹـ‚قپj‚ً‚¢‚¢‚ـ‚·پ@پ@ پ@پ@پ@پuŒ’چNگf’fپv‹y‚رپu—\–hگعژيپv‚حگEˆُ‚ھژq‚ة“¯چs‚µ‚ؤژَ‚¯‚³‚¹‚éڈêچ‡‚ةŒہ‚è‚ـ‚· |
پ@پ@ƒAپ@ٹwچZ‹³ˆç–@‘و‚Pڈً‚ة‹K’è‚·‚éڈ¬ٹwچZپA’†ٹwچZپA’†“™‹³ˆçٹwچZپA–سٹwچZپAکWٹwچZپAژx‰‡ٹwچZ‹y‚ر—c’t‰€ پ@پ@ƒCپ@ژ™“¶•ںژƒ–@‘و‚Vڈً‚ة‹K’è‚·‚é•غˆçڈٹ پ@پ@ƒEپ@‚»‚ج‘¼پAƒA–”‚حƒC‚ةڈ€‚¸‚éژ{گف‚إ‚ ‚ء‚ؤگlژ–ˆدˆُ‰ï‚ھ”F‚ك‚é‚à‚ج |
پy—لپz“üٹwپi‰€پjژ®پA‘²‹ئپi‰€پjژ®پAژِ‹ئپi•غˆçپjژQٹدپAچ§’k‰ïپA‰ئ’ë–K–âپA‰^“®‰ïپE‘جˆç‘ه‰ïپAٹwڈKپiگ¶ٹˆپj”•\‰ïپAŒً’تˆہ‘Sژw“±پAگiکHگà–¾‰ïپiڈٹ‘®چZ‚ج‚à‚جپj“™ پ@پ@ |
پ@پ@ژq‚ھچفگذ‚·‚éٹwچZ“™‚جPTAٹˆ“®‚ة‚ح‘چ‰ïپA–ًˆُ‰ïپAˆدˆُ‰ïپA•”‰ïپAڈ„‰ٌ•â“±پAŒً’تچ¸ژ@پAƒvپ[ƒ‹“–”ش“™‚ھ‚ ‚è‚ـ‚·پB |
ƒچپ@گEˆُ‚ھژں‚ج‡@‡A‚جژ–—R‚ةٹY“–‚µپC—v‰îŒىژز‚ج‰îŒى‚ً‚·‚éڈêچ‡پC—ï”N‚ة‚¨‚¢‚ؤ‚T“ْپi—v‰îŒىژز‚ھ‚Qگlˆبڈم‚ ‚é‚ئ‚«‚ح‚P‚O“ْپj‚ً‰z‚¦‚ب‚¢
پ@”حˆح“à‚إ•K—v‚ئ”F‚ك‚é“ْ–”‚حژٹش‚ئ‚ê‚ـ‚·پB
پ@پ@‡@پ@‘خڈغ‚حپCگEˆُ‚ھ”z‹ôژزپC•ƒ•êپCژqپC”z‹ôژز‚ج•ƒ•ê“™‚إ•‰ڈپCژ¾•a–”‚حکV—î‚ة‚و‚è‚P“ْˆبڈم“ْڈيگ¶ٹˆ‚ً‰c‚ق‚ج‚ةژxڈل‚ھ‚ ‚é‚à‚ج‚ً
پ@پ@پ@‰îŒى‚·‚éڈêچ‡‚إ‚ ‚éپB
پ@پ@‡Aپ@پu“ْڈيگ¶ٹˆ‚ً‰c‚ق‚ج‚ةژxڈل‚ھ‚ ‚é‚à‚ج‚ج‰îŒىپv‚ة‚آ‚¢‚ؤ
پ@پ@پ@پ@•a–¼“™‚ج”@‰½‚ة‚©‚©‚ي‚炸پC—v‰îŒىژز‚ج‰îŒى‚ً•K—v‚ئ‚·‚éڈَ‘ش‚ة’…–ع‚µ‚ؤ”»’f‚·‚éپB
پ@پ@پ@[—لژ¦]
پ@پ@پ@پ@پ@پEƒKƒ“‚ج‚½‚كگQ‚½‚«‚è‚ئ‚ب‚ء‚½•ƒ‚جگHژ–پC”rں•پC“ü—پ“™گg‚ج‰ٌ‚è‚جگ¢کb‚ً‚·‚éڈêچ‡پB
پ@پ@پ@پ@پ@پEƒCƒ“ƒtƒ‹ƒGƒ“ƒU‚ةœëٹ³‚µپCچ‚”M‚ھ‘±‚¢‚ؤ‚¢‚éژq‚ا‚à‚جگHژ–پC”rں•پC“ü—پ“™گg‚ج‰ٌ‚è‚جگ¢کb‚ً‚·‚éڈêچ‡پB
پ@پ@پ@پ@پ@پEکV—î‚ج‚½‚كŒِ‹¤Œً’ت‹@ٹض‚ج—ک—p‚ھچ¢“ï‚ب•ê‚ً“œ”A•aژ،—أ‚ج‚½‚ك•a‰@‚ض‘—Œ}‚·‚éڈêچ‡پB
پ@پ@پ@پ@پ@پEگ¸گ_ڈم‚جڈلٹQ‚ج‚½‚كپCگHژ–پC”rں•پC“ü—پ“™‚ھ‚إ‚«‚ب‚¢”z‹ôژز‚جگg‚ج‰ٌ‚è‚جگ¢کb‚ً‚·‚éڈêچ‡پB
ƒnپ@’jگ«گEˆُ‚ة‚آ‚¢‚ؤ‚حپAچب‚جژY‘O‚WڈT
پi‘½‘ظ”DگP‚جڈêچ‡‚ح‚P‚SڈTپjژYŒم‚WڈT‚جٹْٹش’†‚ةŒہ‚èپAژں‚ج‡@‡A‚جڈêچ‡پA•ت‚ة‚W“ْˆب“à‚ج“ْ‚ـ‚½‚حژٹش‚إژو“¾‚إ‚«‚éپB
‡@چب‚جڈoژY‚ة”؛‚¤•t‚«“Y‚¢‚â‰îڈ•“™‚ًچs‚¤ڈêچ‡
‡Aچب‚جژY‘OژYŒمپiژY‘O‚WڈTژYŒم‚WڈTپjٹْٹش’†‚ةپAڈoژY‚ة‚©‚©‚éژq–”‚حڈم‚جژqپiڈ¬ٹwچZڈAٹw‘Oپj‚ً—{ˆç‚·‚éڈêچ‡
“ء•ت‹x‰ةگ\گ؟ڈ‘‚ج”ُچl—“‚ةپA‘خڈغ‚ئ‚ب‚éژز‚جژپ–¼پA”N—î‹y‚ر‘±•؟پA•‰ڈپAژ¾•a‚à‚µ‚‚حکV—î‚جڈَ‹µ–”‚حپAچsژ––¼“™‚ًٹبŒ‰‚ة‹L“ü‚µ‚ـ‚·پB”z‹ôژز‚ج•ھ‚ׂٌ‚جڈêچ‡‚ح•ھ‚ׂٌ—\’è“ْ–”‚ح•ھ‚ׂٌ“ْ‚ً‹L“ü‚·‚é
پ@پ@پ@پ@پ@پ@
![]() ‘و‚P‚Pڈً‚ج‚P‚Qچ†
‘و‚P‚Pڈً‚ج‚P‚Qچ†
پ@گEˆُ‚جچ¥ˆ÷‚جڈêچ‡
پ@‚W“ْ‚ً’´‚¦‚ب‚¢”حˆح“à‚إ•K—v‚ئ”F‚ك‚é“ْ–”ژٹش‚ئ‚ê‚ـ‚·
![]() ‘و‚P‚Pڈً‚ج‚P‚Rچ†
‘و‚P‚Pڈً‚ج‚P‚Rچ†
| •ت•\‘و‚Rپ@ |
|||
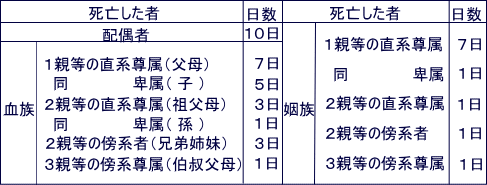 پ@ |
|||
| ”ُچl | |||
| ‚Pپ@ | گEˆُ‚ئگ¶Œv‚ًˆê‚ة‚·‚éˆ÷‘°‚جڈêچ‡‹y‚رگEˆُ‚ج”z‹ôژز‚ھ‘rژه‚ئ‚ب‚é‚ئ‚«‚جˆ÷‘°‚جڈêچ‡‚حپCŒŒ‘°‚جڈêچ‡‚ةڈ€‚¸‚é | ||
| ‚Q | ‚¢‚ي‚ن‚é‘مڈP‘ٹ‘±‚جڈêچ‡‚ة‚¨‚¢‚ؤچص‹ï“™‚ًŒpڈ³‚·‚éژز‚حپC‚Pگe“™‚ج’¼ŒnŒŒ‘°پi•ƒ•ê‹y‚رژqپj‚ةڈ€‚¸‚é | ||
| ‚R | گEˆُ‚ھ‘’‹V‚ج‚½‚ك‰“ٹu‚ج’n‚ة—·چs‚·‚é•K—v‚ھ‚ ‚éڈêچ‡‚حپC‚»‚ج‰•œ‚ة—v‚µ‚½“ْگ”‚ج‰ءژZ‚ً”F‚ك‚邱‚ئ‚ھ‚إ‚«‚é | ||
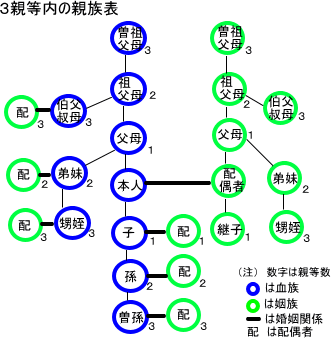 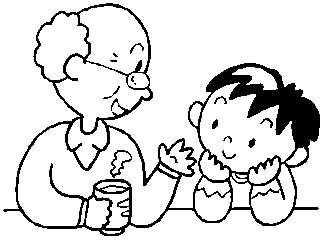 |
|||
![]() ‘و‚P‚Pڈً‚ج‚P‚Sچ†
‘و‚P‚Pڈً‚ج‚P‚Sچ†
پ@•ƒ•êپC”z‹ôژزپC‹y‚رژq‚جچص“ْ‚جڈêچ‡
چص“ْ‚ئ‚حپ@پ@•§‹³‚ة‚¨‚¯‚é‚S‚X“ْپC‚P‚O‚O“ْپC‚P‰ٌٹُپC‚R‰ٌٹُپC‚V‰ٌٹُ“™‚ج‚²‚ئ‚ژذ‰ïˆê”ت‚جٹµڈKڈم‚ج‚à‚ج‚ً‚¢‚¢‚ـ‚·
![]() پ@پ@پ@ٹµڈKڈم•K—v‚ئ”F‚ك‚é“ْ–”‚حژٹشپ@‚ئ‚ê‚ـ‚·
پ@پ@پ@ٹµڈKڈم•K—v‚ئ”F‚ك‚é“ْ–”‚حژٹشپ@‚ئ‚ê‚ـ‚·
![]() ‘و‚P‚Pڈً‚ج‚P‚Tچ†
‘و‚P‚Pڈً‚ج‚P‚Tچ†
گEˆُ‚ھ‰ؤ‹G‚ة‚¨‚¯‚éگSگg‚جŒ’چN‚جˆغژ‹y‚ر‘گi‚â‰ئ’ëگ¶ٹˆ‚جڈ[ژہ‚ًگ}‚éڈêچ‡پ@
‚VŒژ‚P“ْ‚©‚ç‚P‚OŒژ‚R‚P“ْ‚ـ‚إ‚جٹْٹش“à‚ة‚¨‚¢‚ؤپCڈT‹x“ْپE‹x“ْ‚ًڈœ‚¢‚ؤŒ´‘¥‚ئ‚µ‚ؤکA‘±‚·‚é‚U“ْˆب“à‚ج“ْ
پ@پ@‚ھ‚ئ‚ê‚ـ‚·
گSگg‚جŒ’چN‚جˆغژ‹y‚ر‘گi‚â‰ئ’ëگ¶ٹˆ‚جڈ[ژہپEپEپEپEپEپ@
‹ï‘ج“Iژ–چ€‚ئ‚µ‚ؤ‚حپC‹x—{پCƒXƒ|پ[ƒcپC—·چs“™‚ج‘¼پC•وژQپCچص—ç“™‚جڈ”چsژ–‚ًٹـ‚ق
Œ´‘¥‚ئ‚µ‚ؤکA‘±‚·‚é‚U“ْپ@‚جژوˆµ‚¢‚ة‚آ‚¢‚ؤ‚حپC—ً“ْ‚ة‚و‚é‚à‚ج‚ئ‚µŒِ–±‰^‰cڈم‚ج——R‚ة‚و‚è”C–½Œ ژز‚ة‚¨‚¢‚ؤ“ء‚ة•K—v‚ھ‚ ‚é‚ئ”F‚ك‚éڈêچ‡‚ة‚حپC‚P—ً“ْ‚²‚ئ‚ة•ھٹ„‚إ‚«‚ـ‚·
 پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@
–‚R‚OچخپC–‚S‚OچخپC–”‚ح–‚T‚Oچخ‚ة’B‚µ‚½گEˆُ‚ھگSگg‚جŒ’چN‚جˆغژ‹y‚ر‘گi‚ًگ}‚éڈêچ‡
‚±‚ê‚ç‚ج”N—î‚ة’B‚µ‚½“ْ‚ج—‚“ْˆبŒم‚P”N–ع‚ة“–‚½‚é“ْ‚ـ‚إ‚جٹْٹش“à‚ة‚¨‚¢‚ؤپCڈT‹x“ْ‹y‚ر‹x“ْ‚ًڈœ‚¢‚ؤŒ´‘¥‚ئ‚µ‚ؤکA‘±‚·‚é‚R“ْٹشˆب“à‚ج“ْپ@‚ئ‚ê‚ـ‚·
Œ´‘¥‚ئ‚µ‚ؤکA‘±‚·‚é‚R“ْپ@‚جژوˆµ‚¢‚ة‚آ‚¢‚ؤ‚حپC—ً“ْ‚ة‚و‚é‚à‚ج‚ئ‚µپCŒِ–±‰^‰cڈم‚ج——R‚ة‚و‚è”C–½Œ ژز‚ة‚¨‚¢‚ؤ“ء‚ة•K—v‚ھ‚ ‚é‚ئ”F‚ك‚éڈêچ‡‚ة‚ح‚P—ً“ْ‚²‚ئ‚ة•ھٹ„‚إ‚«‚ـ‚·
![]() ‘و‚P‚Pڈً‚ج‚P‚Vچ†
‘و‚P‚Pڈً‚ج‚P‚Vچ†
گEˆُ‚ھ‚Q‚T”Nˆبڈم‹خ–±‚µ‚½‚±‚ئ‚ة‚و‚èپC”C–½Œ ژز‚©‚ç•\ڈ²‚ًژَ‚¯‚½ڈêچ‡پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@
پ@‚»‚ج•\ڈ²‚ًژَ‚¯‚½“ْˆبŒم‚P”N–ع‚ة“–‚½‚é“ْ‚ـ‚إ‚جٹْٹش“à‚ة‚¨‚¢‚ؤ‚S“ْˆب“à‚ج“ْپ@‚ئ‚ê‚ـ‚·
پ@پ@پi•ھٹ„ژو“¾‰آپj
![]() ‘و‚P‚Pڈً‚ج‚P‚Wچ†
‘و‚P‚Pڈً‚ج‚P‚Wچ†
پ@پ@‚»‚ج‘¼گlژ–ˆدˆُ‰ï‚ھ•K—v‚ئ”F‚ك‚éڈêچ‡
‚½‚ئ‚¦‚خ
گEˆُ‚ھپCŒِ–±ٹO‚ئ‚µ‚ؤچ‘–¯‘جˆç‘ه‰ï–”‚ح‘Sچ‘ڈلٹQژزƒXƒ|پ[ƒc‘ه‰ï‚ة‘IژèپCٹؤ“آ–”‚حƒRپ[ƒ`‚ئ‚µ‚ؤژQ‰ء‚·‚éڈêچ‡
گEˆُ‚ھپC’تگM‹³ˆç‚ج–تگعژِ‹ئ‚ةژQ‰ء‚·‚éڈêچ‡
چZ’·پE‹³ˆُ‚ھپCŒِ“I‹@ٹض‚ـ‚½‚ح‚±‚ê‚ةڈ€‚¸‚é’c‘ج‚جچ\گ¬ˆُ‚ئ‚µ‚ؤٹCٹO—·چs‚·‚éڈêچ‡‚إپC‚»‚جٹCٹO—·چs‚ج–ع“IپC“à—e‚©‚ç‰ھژRŒ§‹³ˆçˆدˆُ‰ï‚ھ“K“–‚ئ”F‚ك‚éڈêچ‡
گEˆُ‚ھپC’n•ûŒِ–±ˆُ–@‘و‚S‚Vڈً‚ج‹K’è‚ةٹî‚أ‚‹خ–±ڈًŒڈ‚ج‘[’u‚ج—v‹پ‚ة‚آ‚¢‚ؤ‚جگRچ¸‚ة—v‹پژز‚ئ‚µ‚ؤڈoگب‚·‚éڈêچ‡‚ـ‚½‚ح“¯–@‘و‚T‚Oڈً‚ج‹K’è‚ةٹî‚أ‚•s—ک‰vڈˆ•ھ‚ةٹض‚·‚é•s•گ\—§‚ؤ‚ة‚آ‚¢‚ؤ‚جŒû“ڑگR—‚à‚µ‚‚ح‚»‚جڈ€”ُژ葱‚ة•s•گ\—§گl‚ئ‚µ‚ؤڈoگب‚·‚éڈêچ‡
‚ب‚اپ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@
”ٌڈي‹خچuژt‚حپEپEپEپE
‘S‚ؤ—L‹‹‹x‰ة
| چ€پ@–ع | ژ–پ@—R | “ْپ@گ”پ@“™ |
| پ@Œِ–¯Œ چsژg | پ@‘I‹“Œ “™‚جŒِ–¯Œ چsژg‚ً‚·‚éڈêچ‡ | پ@•K—v‚ئ”F‚ك‚ç‚ê‚éٹْٹش |
| پ@ٹ¯Œِڈگڈo“ھ | پ@چظ”»ˆُ“™‚ئ‚µ‚ؤٹ¯Œِڈگ‚ضڈo“ھ‚·‚éڈêچ‡ | پ@•K—v‚ئ”F‚ك‚ç‚ê‚éٹْٹش |
| پ@Œ»ڈZڈٹ–إژ¸“™ | پ@چذٹQ‚ة‚و‚茻ڈZڈٹ‚ھ–إژ¸پE‘¹‰َ“™‚µ‚½ڈêچ‡ | پ@‚PڈTٹش‚ً’´‚¦‚ب‚¢ٹْٹش |
| پ@ڈo‹خچ¢“ï | پ@چذٹQ‚âŒً’ت‹@ٹض‚جژ–Œج“™‚ة‚و‚èڈo‹خ‚ھچ¢“ï‚بڈêچ‡ | پ@•K—v‚ئ”F‚ك‚ç‚ê‚éٹْٹش |
| پ@‘ق‹خ“rڈم | پ@چذٹQ“™‚ةچغ‚µ‘ق‹خ“rڈم‚جٹ댯‚ً‰ٌ”ً‚·‚éڈêچ‡ | پ@•K—v‚ئ”F‚ك‚ç‚ê‚éٹْٹش |
| پ@ٹُˆّ | پ@گe‘°‚ھژ€–S‚µ‚½ڈêچ‡ | پ@ژ€–S‚µ‚½گe‘°‚ة‰‚¶‚ؤ’è‚ك‚é“ْگ”پiچإ‘ه‚P‚O“ْپj‚جپ@ پ@”حˆح“à‚جٹْٹش |
| پ@Œ‹چ¥ | پ@Œ‹چ¥‚·‚éڈêچ‡ | پ@Œ‹چ¥“ْ‚ج‚T“ْ‘O‚©‚猋چ¥“ْŒم‚PŒژ‚ج”حˆح“à‚إ پ@کA‘±‚T“ْˆب“à‚جٹْٹش |
| پ@‰ؤ‹G | پ@”C—pٹْٹش6Œژˆبڈم‚جڈêچ‡ | پ@7Œژ1“ْ‚©‚ç10Œژ31“ْ‚ـ‚إ‚ج”حˆح“à‚إڈT–”‚ح”N‚ج پ@‹خ–±“ْگ”‚ة‰‚¶‚ؤ’è‚ك‚é“ْگ”پiچإ‘ه3“ْپj |
| پ@”DژY•w‚ج پ@Œ’چNŒںچ¸پE•غŒ’ژw“±پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ |
پ@”DگP’†–”‚حڈoژYŒم1”Nˆب“à‚جڈ—گ«‚ھ•êژq•غŒ’–@‚ج پ@‹K’è‚ة‚و‚é•غŒ’ژw“±‚⌒چNگfچ¸‚ًژَ‚¯‚éڈêچ‡ |
پ@”DگP23ڈT‚ـ‚إ‚ح4ڈT‚ة1‰ٌپA”DگP–24ڈT‚©‚ç پ@–35ڈT‚ـ‚إ‚ح2ڈT‚ة1‰ٌپA”DگP–36ڈT‚©‚ç•ھ•ط پ@‚ـ‚إ‚ح1ڈT‚ة1‰ٌپAژYŒم1”N‚ـ‚إ‚ح‚»‚جٹش‚ة1‰ٌپA پ@‚»‚ج“s“x•K—v‚ئ”F‚ك‚ç‚ê‚éژٹش |
| پ@”DگP’†‚ج’ت‹خٹةکa | پ@”DگP’†‚جڈ—گ«‚ھ’ت‹خ‚ة—ک—p‚·‚éŒً’ت‹@ٹض‚جچ¬ژG‚جپ@ پ@’ِ“x‚ھ•êژq‚جŒ’چN•غژ‚ة‰e‹؟‚ھ‚ ‚éڈêچ‡ |
پ@‹خ–±ژٹش‚جژn‚ك–”‚حڈI‚ي‚è‚ة1“ْ1ژٹش‚ً پ@’´‚¦‚ب‚¢”حˆح‚إ•K—v‚ئ”F‚ك‚ç‚ê‚éژٹش |
| ڈoگ¶ƒTƒ|پ[ƒgپ¦ | پ@•s”Dژ،—أ‚ة‚و‚é’ت‰@‚جڈêچ‡ | پ@5“ْ‚ج”حˆح“à‚ج“ْ–”‚حژٹشپi‘جٹOژَگ¸–”‚حŒ°”÷ژِگ¸ پ@‚جڈêچ‡‚ح10“ْپj |
| ”z‹ôژزڈoژYپ¦ | پ@چب‚جڈoژY‚ةŒW‚é“ü‘ق‰@‚ج•t‚«“Y‚¢پAڈoژYژ‚ج•t‚«“Y‚¢ پ@“ü‰@’†‚جگ¢کbپAژq‚جڈoگ¶‚ج“ح‚¯ڈo“™‚جڈêچ‡ |
پ@چب‚جڈoژY“ü‰@“ْ‚©‚çڈoژYŒم2ڈTٹش‚ـ‚إ‚جٹْٹش“à‚ة پ@2“ْ‚ج”حˆح“à‚ج“ْ–”‚حژٹش |
| ˆçژ™ژQ‰ءپ¦ | پ@گ¶‚ـ‚ꂽژq–”‚حڈ¬ٹwچZڈAٹw‘O‚جژq‚ً—أˆç‚·‚éڈêچ‡ | پ@ڈoژY—\’è“ْ‚ج6ڈTٹش‘O‚©‚çڈoژYŒم8ڈTٹش‚ـ‚إ‚جٹْٹش پ@“à‚ة5“ْ‚ج”حˆح“à‚ج“ْ–”‚حژٹش |